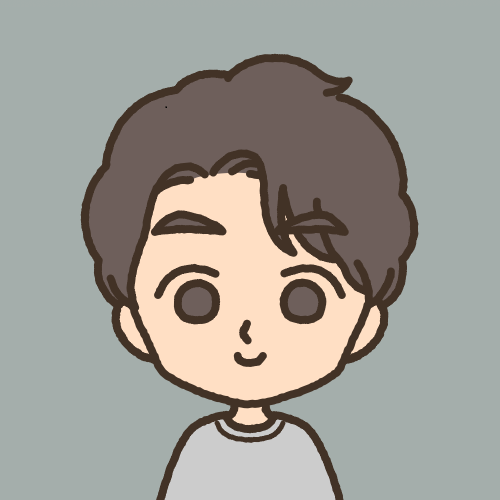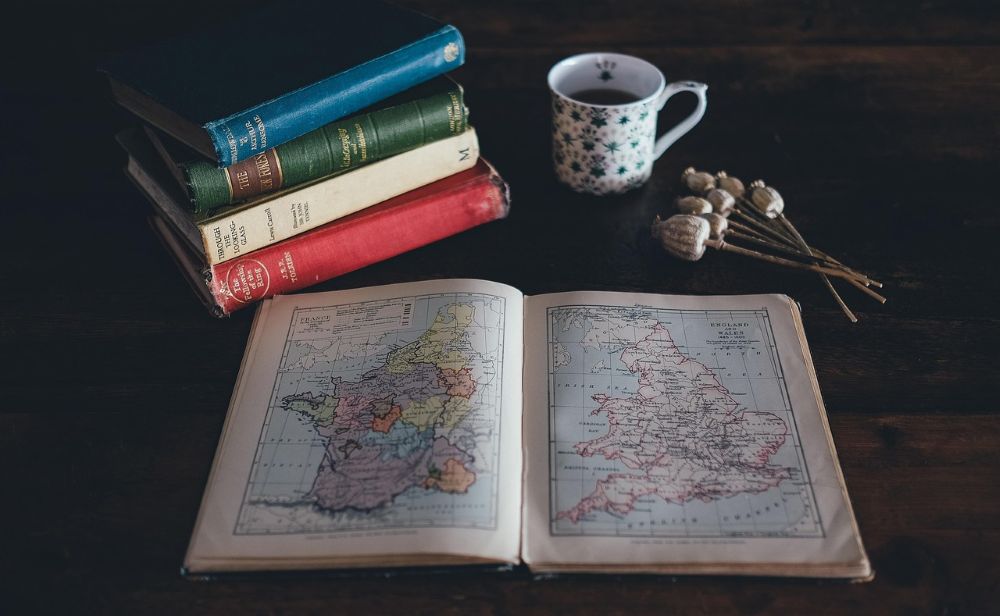みなさんこんにちは、読書とランニングとアルコールが大好きな真面目人間タカアシストです。
突然ですが、みなさんは勉強をするメリットについてどう考えていますか?
様々な考え方があると思いますが、私が思うメリットは知識が増えることで視野が広がる、将来自分がやりたいことの選択肢が増えるといったメリットが思い浮かびました。では、デメリットはどうでしょう。おそらく、ほとんど出てこないのではないかと思います。私も考えてみましたが、「知識の習得に時間がかかる」くらいしか思いつきませんでした。
そんな良いことだらけの勉強ですが、ほとんどの方は勉強好きじゃないですよね、、、
ある調査によると勉強が好きな人の割合は、小学生で約6割、中学生で約4割、高校生、社会人で約3割と勉強が難しくなるごとに好きな人が減っています。ですが、社会人のみなさんは痛感していると思いますが勉強というのは学生で終わりではなく、働くようになっても「影」のように付いてきます。
効果のある勉強法については、多くの方が情報発信していると思うので、今回は逆に効果の「薄い」勉強法を紹介したいと思います。なので、紹介した勉強法はしないことをおすすめします。
効果が薄い勉強法3選

効果が薄い勉強法①「再読(繰り返し読む)」
これは、教科書や参考書の内容を繰り返し読む方法です。勉強している多くの人が行っている方法ではないでしょうか?
この方法は、短期的に記憶するのには効果があるようですが、長期的な記憶にするのには効果が薄いようです。勉強で良い成績を取るには勉強したことを長期記憶に残す必要があるので効果のある勉強法とは言えなそうです。
この方法の厄介なところは、何回も読んでいるとスラスラ読めるようになってしまうため内容を理解できたと錯覚してしまうところです。
ある研究結果では、同じ内容のものを2回読んだ学生と4回読んだ学生を比べてどちらが記憶できているかテストしたところ成績に変わりがなかったという報告も出ています。
効果が薄い勉強法②「ハイライトやアンダーラインを引く」
教科書や参考書の重要な部分に蛍光ペンでマークしたり、赤ペンでアンダーラインを引く方法です。
この勉強法は、重要な部分を見極めるスキルがある人にとっては効果のある勉強法ですが、すべての人がこの素晴らしいスキルを持っているわけではないので効果が薄い勉強法になっています。
重要な部分を見極めるスキルを持っている人でも注意してほしい点があります。それは、ハイライトやアンダーラインを引いたらそこで満足しないことです。なぜ?どうして?と自分自身に質問し詳しい内容までしっかり学習することが大切です。
効果が薄い勉強法③「内容をノートにただ書き写す、まとめる」
教科書や参考書の内容をノートに書き写す、内容をまとめる勉強法です。
この方法のデメリットは、教科書や参考書の内容をノートに書き写すのは、「書く」という行為が多くなり勉強をしたつもりになってしまうことです。そもそも、「書く」という行為自体が高度なスキルなので、書くことだけに集中してしまい、内容を理解するところまで辿り着けません。そして、時間をかけて書いたものも時間が経つにつれて忘れていきます。これでは、せっかく頑張って書いた時間がもったいないですよね。
ですが、内容をまとめるスキルが高い人にとってはこの方法でも効果があるという研究結果もあります。この方法もすべての人に効果のある勉強法とは言えないので、効果の「薄い」勉強法にしました。
この「ノートの内容を書き写すだけ、まとめる」勉強法をしていて成績が伸び悩んでいる人は別の勉強法を試してみましょう。
まとめ

今回は、学生さんや資格の勉強を頑張っている人に向けて効果の「薄い」勉強法について紹介しました。現在、勉強は頑張っているのに成績が伸び悩んでいる人は今回紹介した勉強法をしているのであれば、別の勉強法を試してみましょう。
【参考文献】
「科学的根拠に基づく最高の勉強法」 著者:安川康介(2024,株式会社KADOKAWA)